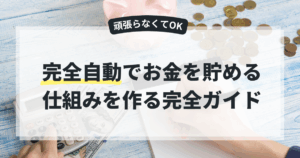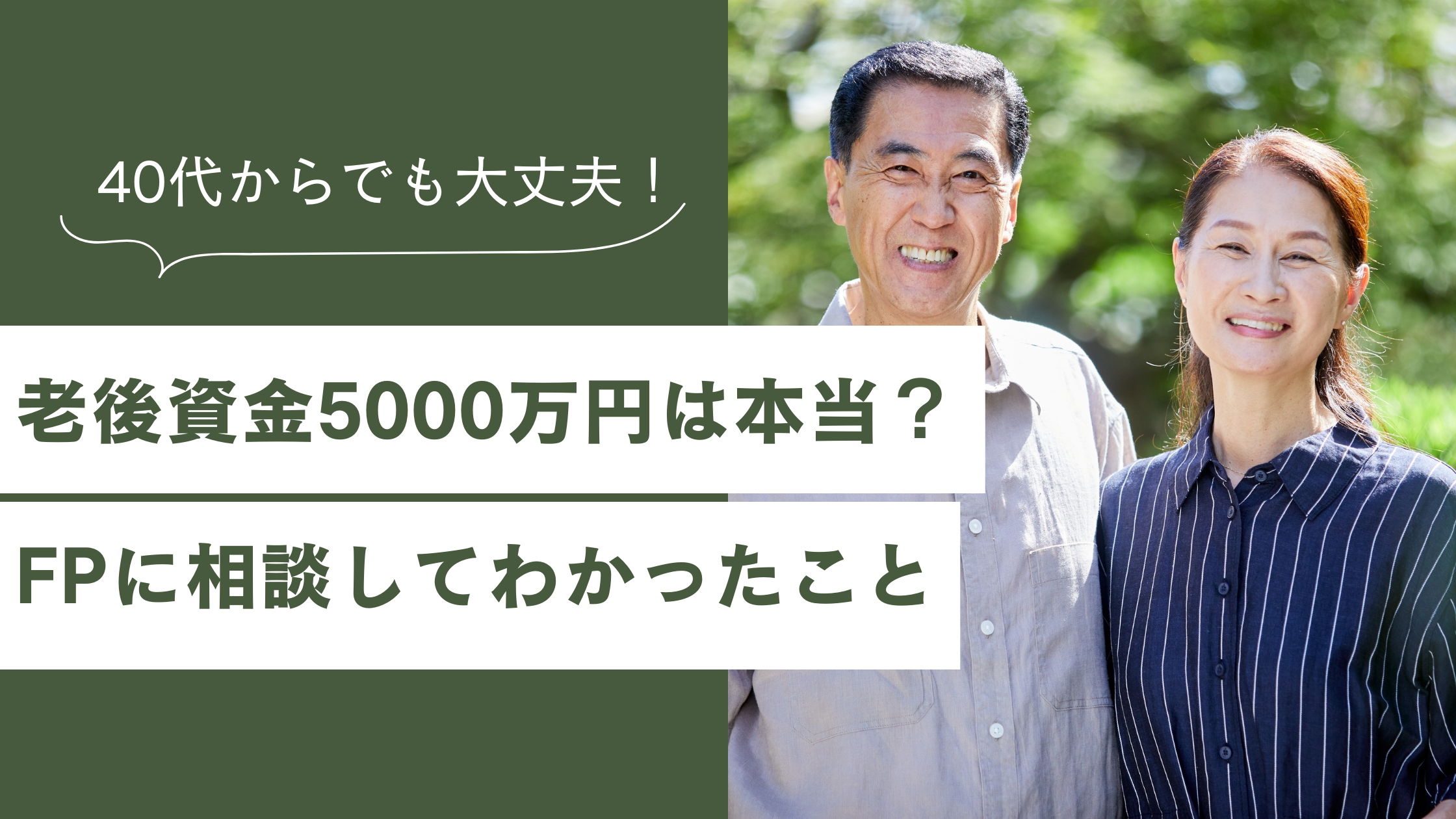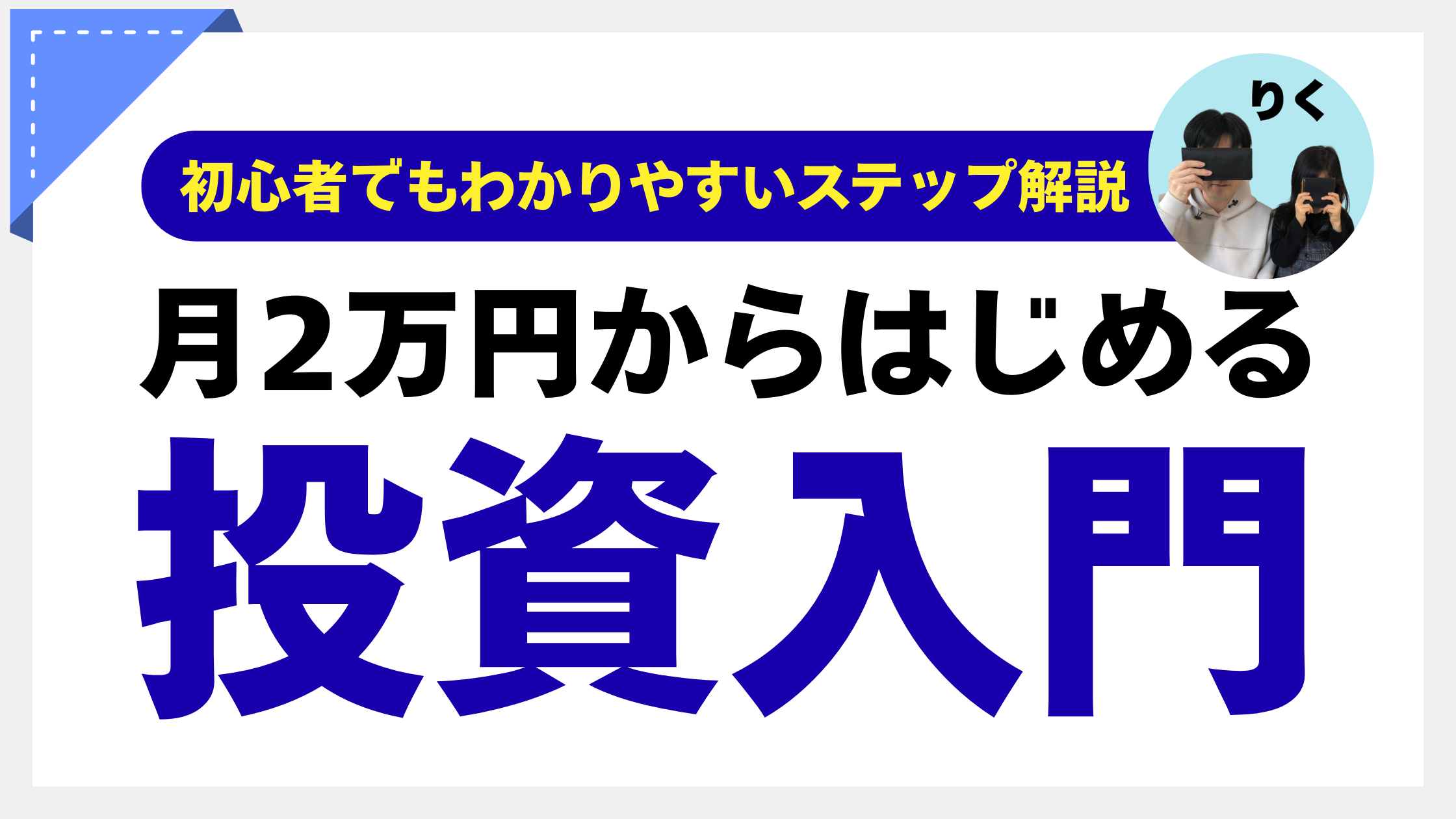「子どもが生まれたら学資保険に入るもの」
親やママ友にそう言われたことはありませんか?
私自身もそうでした。子どもの教育費は学資保険で準備するのが正解だと思い込んでいました。
でも実際に調べてみると、学資保険は増えるどころかインフレで実質目減りしているんです!
そこで出会ったのが【新NISA×収入保障保険】という考え方です。
「増やす」と「守る」を分けて教育費を準備する方法で、学資保険より効率的かつ安心感が高いのが特徴です。
- なぜ学資保険は中途半端なのか?
- 新NISA×収入保障保険が合理的な理由
- どのくらい差が出るのかシミュレーション
- 我が家の教育費1,000万円達成までのロードマップ
を分かりやすく解説していきます。
学資保険は「貯める」も「守る」も中途半端!なぜ選ぶと損をするのか?

多くのママが選ぶ学資保険ですが、実は「貯める」商品としても「守る」商品としても中途半端な存在です。
理由は以下の3つ。
① お金がほとんど増えない
学資保険の返戻率は105~110%程度、年利に直すと0.3%前後です。
例えば毎月2万円を15年間積み立てて360万円払っても、受け取れるのは約396万円。
増えたのはたった36万円ほどで、これでは教育費という大金を準備するのに「効率的」とは言えません。
②インフレに弱い
物価が毎年2%ずつ上昇した場合、10年後には20%お金の価値が減ってしまいます。
実際に2025年4月には消費者物価指数が前年同月比3.6%上昇しました。
これは2025年度通年で2%台になるとの予想もありましたが、食品価格の高止まりなどで3%台が続いており、企業の「値上げ意向も強く、物価上昇率が下がるか」はかなり不透明。
学資保険で少し増えたとしても、インフレでその価値は簡単に消えてしまう可能性があるのです。
③ 保障も限定的
「親に万一があったら保険料が免除される」というのが学資保険の大きな特徴。
ただし“満額もらえる”わけではなく、契約内容によっては途中の給付金が減額されるなど条件があるため、過信はできません。
学資保険は「お金を増やす力」も「保障」としての安心感も中途半端。
だからこそ、「貯める」と「守る」を切り分けて考える方が合理的なのです。
新NISA×収入保障保険で「増やす」と「守る」の最強の解決策

学資保険の弱点を補う方法が、新NISAと収入保障保険を組み合わせる考え方です。
新NISAで「増やす」
新NISAの最大の魅力は、
- 投資信託で長期・分散投資ができる
- 運用益がすべて非課税になる
もし一般の投資で100万円増えたら約20万円が税金で引かれますが、新NISAなら100万円まるごと教育費にできるのです。
これは国が用意した最大の優遇策です。
収入保障保険で「守る」
収入保障保険は掛け捨て型なので、保険料が学資保険よりも大幅に安くなります。
学資保険をやめて浮いた保険料を、すべて新NISAに回すことができる。
これが高効率に教育資金を貯める最大の秘密です。
このように役割を分けることで、学資保険より効率的かつ安心感のある教育資金の準備が可能になります。
シミュレーションで比較(数字で納得)
では、実際にどのくらい差が出るのかシミュレーションしてみましょう。
学資保険の場合
新NISAで運用した場合(年利5%想定)
差額は約120万円。
これは大学の入学金や半年分の授業料に匹敵する金額です。
賢くNISAを活用するだけで、子どもの選択肢を広げることができます。
同じ積立額でも、NISAを活用するだけでこれほど差が出る可能性があるのです。
さらに、収入保障保険を組み合わせれば「万一のリスク」もカバーでき、より安心して教育費を準備できます。
【再現性重視】教育費1,000万円達成までのロードマップ

では、実際に教育費1,000万円達成までの道のりを紹介します!
教育費準備、成功を分けた3つのステップ
僕自身、貯金ゼロから4年で資産1000万作りました。
その経験からも言えることですが、成功を分けたのは、もちろんお金の勉強をしてつけた知識も必要ですが、それ以上に、このシンプルな3つのステップが重要です。
①「ゴール」の明確化
僕はまずFPさんに相談して、「いつまでに、いくら必要なのか?」をシミュレーションで明確にしました。
私の場合は「子ども1人なので、その大学費用を、高校卒業までに1,000万円貯める」という具体的なゴールが決まりました(まだ、幼稚園なので教育費自体は貯めている最中です)。
目標額がはっきりすると、毎月の積立額も逆算できるようになり、モチベーションが格段に上がります。
②「手段」の最適化
目標が決まったら、当初、頭に合った学資保険はやらずに【新NISA×収入保障保険】に手段を切り替えました。
これにより、これまで保障と貯蓄に分散していたお金が非課税で増えるNISAに一本化され、貯蓄のスピードが劇的に向上しました。
③「自動化」と「ほったらかし」
積立額が決まったら、あとは自動引き落としを設定し、完全に「ほったらかし」
多忙なシンパパの僕だけでなく、ワーママにとって、毎月手動で管理するのは大変、面倒です。
銀行口座と同じ感覚で、自動で積立・運用される仕組みを作ったことが、4年で1,000万円達成という結果につながりました。
最も重要なターニングポイントは「プロに相談」
いかがでしたか? 難しい個別株の売買や、複雑な管理は一切ありません。
最初に正しい仕組みを作って、あとは自動で運用するだけです。
このロードマップにおいて、最も重要なターニングポイントとなったのは「最初のFP相談」でした。
もしあの時、教育費のシミュレーションを作ってもらっていなければ、未だに「増えない学資保険」を続けていたかもしれません。
あなたも「どこから手をつけていいか分からない」と悩んでいるなら、まずはあなたの家庭だけのロードマップを作ってもらいましょう。
家計に合わせた積立の工夫
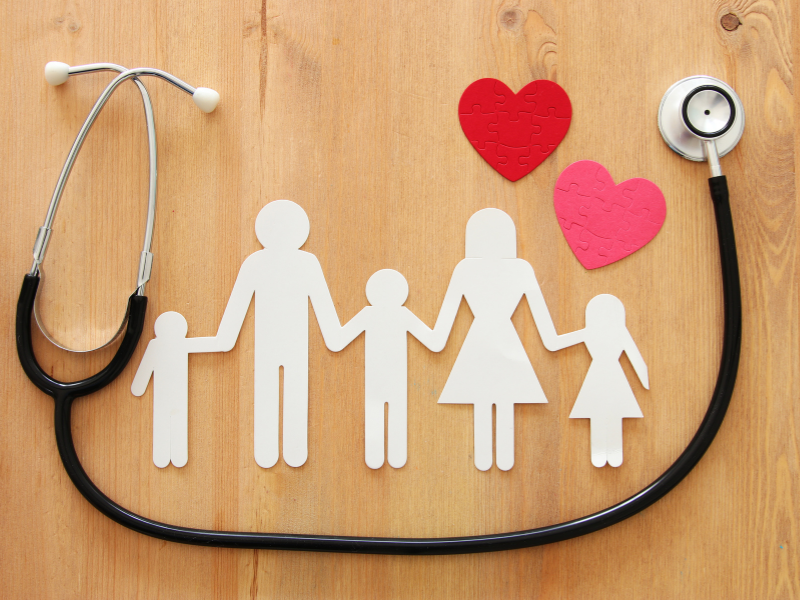
教育資金の準備で大切なのは、家庭のライフステージに合わせて調整することです。例えば…
- 子どもが小さいうちは出費が少ない → 積立を多めに
- 中学・高校で塾やスマホ代が増える → 積立を控えめに
- 児童手当はそのまま新NISAに回す → 教育資金に直結
無理にずっと一定額を積み立てる必要はありません。
「早いうちに多めに積み立てる」のが効率よく貯めるコツです(投資の最大の強みは「複利」)。
まずはFP相談のすすめ

まずは自分に合ったシミュレーションのためにプロのFPに相談するのがおすすめです。ただし、教育費の必要額は家庭によって大きく異なります。
・公立か私立か?
・自宅通学か、ひとり暮らしか?
・大学は文系か理系か?
・給付型の奨学金など受けることが可能か?
これらによって必要なお金は数百万円単位で変わります。
あなたの家庭の場合、大学までにいくら必要か正確に把握していますか?(できていればOK)
もし、正確に必要な額が把握できていないのであれば、FP(ファイナンシャルプランナー)に教育費のシミュレーションを1度作ってもらうことを強くおすすめします。
FPに相談すれば、現在の貯蓄額、理想の進路、給与の変化などを総合的に分析し、『あなただけの教育資金のロードマップ』を数字で作成してもらえます。
僕自身もFPに相談したことで、「いつまでに」「いくら必要で」「毎月いくら積み立てればいいか」が数字で見える化できたことで、将来の不安が一気に解消されました!
まとめ~「増やす」と「守る」で教育費の不安を解消しよう!

学資保険は「増やす」も「守る」も中途半端です。なので、新NISAで効率よく増やしながらも、収入保障保険で守るのが合理的。
まずは、具体的にどれくらいの金額が我が家では必要になるのか?家計に合わせた積立とFP相談で、自分の家庭に合った“正解”を見つけることが大切。
子どもの未来のために、今からでも効率よく教育資金を準備していきましょう。
※本記事は、一般的な金融知識や教育資金の貯め方に関する情報提供を目的としており、特定の商品やサービスの勧誘を行うものではありません。投資信託や保険商品にはリスクがあり、元本が保証されるものではありません。実際の運用成果は、市場環境や契約内容などによって変動します。
※学資保険・NISA・iDeCo・収入保障保険などの制度・商品は、個々の状況(収入・家族構成・ライフプラン)によって最適解が異なります。実際にご検討される際は、必ず金融機関・保険会社・専門家(ファイナンシャルプランナー等)にご相談ください。
※当サイトの情報を利用することによって生じたいかなる損失・トラブルについても、当方は責任を負いかねます。ご理解の上、ご自身の判断と責任でご利用ください。